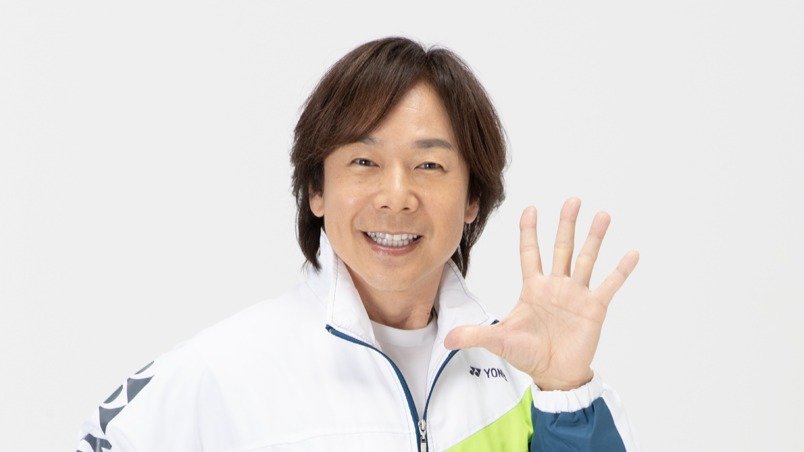新人看護職向けコラム
全盲弁護士1年目を振り返って

「この訴状の書き方は何だ! お前はそれでも弁護士か!」
オフィスに怒声が響き、事務員の女性が息を飲んでこちらを見る。僕が弁護士になったばかりのころ、僕の職場ではそんな光景が連日繰り広げられていた。
そう。怒鳴られているのは僕だ。
司法試験に合格した後、「司法修習」という約1年の研修を終えて、2007年12月、渋谷にある法律事務所に入所した。
事務所には僕を含めて12人の弁護士が在籍していたが、先輩はプロ意識の高い人ばかりで、皆温かく、そして厳しい。もちろん、仕事の上で一切の手加減はない。
弁護士の仕事には依頼人の人生を左右するような重大な事案が多く、ミスは許されない。僕は全盲の障害を持っているが、依頼者にとっては担当の弁護士の目が見えようが見えまいが関係ない。だから当然、僕にも健常者と同じレベルの仕事が求められる。
あれから18年がたち、今では僕も自分の法律事務所を構えて仕事をしている。
振り返ってみると、先輩の厳しい指導も、僕のためを思えばのことだったのだとわかる。
今は大きいものから小さいものまで合わせると、平均して30件ほどの事件や相談を同時並行で処理している。この数字は一般の弁護士とそう変わらないと思うが、目で情報をインプットできないので、1つの案件を処理するのに健常者よりも余計に時間がかかる。
その分、どうしても自分の時間を割いて仕事に充てることになる。もう少し家族とゆっくり過ごせたらと思うときもある。趣味のギターの腕を磨いたり、世界各地を旅したりもしてもみたい。だけどまずは、一人ひとりの依頼者と丁寧に向き合って、仕事の質では超一流だといわれるようになりたいと思っている。
少し話は変わるが、先日読んだ本の中で、村上春樹が、「人生は基本的に不公平なものである。それは間違いのないところだ。しかし、たとえ不公平な場所にあっても、そこにある種の「公正さ」を希求することは可能であると思う。それには時間と手間がかかるかも知れない。あるいは、時間と手間をかけただけ無駄だったね、ということになるかもしれない。そのような「公正さ」に、あえて希求するだけの価値があるかどうかを決めるのは、もちろん個人の裁量である。」と書いているのを見つけた。
僕もこれには同感だ。視覚障害を持ちつつ弁護士をやっていると、膨大な活字の書面や資料を前にしたときなど、ああ自由にこれらを読めればなどともどかしい思いをすることもあるし、図表や写真が読めなくて深刻な不便を感じることもある。
しかし、たまに、事件処理が終わった後など、依頼者から、「今回、先生のようにがんばっている方にお会いできて本当によかったです」などと言っていただくことがある。
そんなときには、「そうですか、そう言っていただけるとうれしいですよ。」などとクールに決めてはみるが、後で「僕の障害もまんざら捨てたものではないな」と、一人でにやにやしちゃうのである。
僕はこれからも、人生は不公平だと嘆くよりは、自分のできる限りのことをして、自分なりの「公正さ」を求め続けたいと思っている。